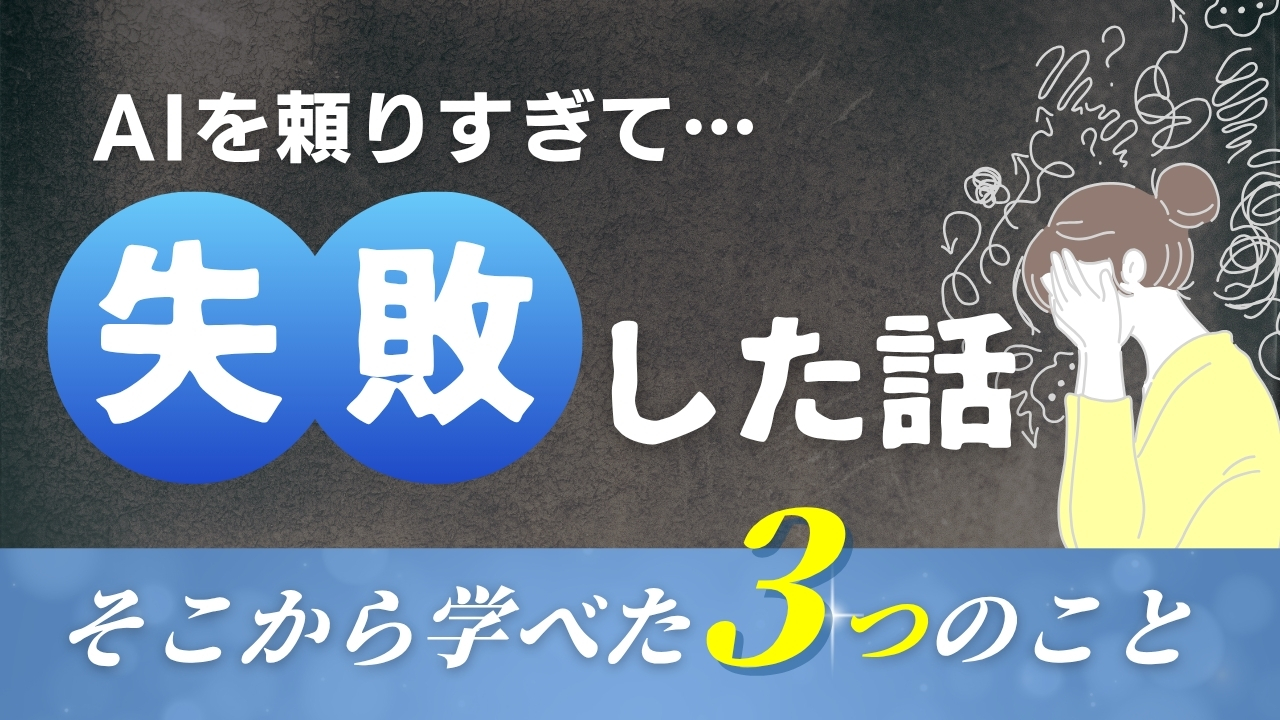
「AIを活用すれば、簡単に副業で収入が得られる」
そんな言葉を目にした私は、ChatGPTをはじめとする生成AIを知り、「これがあれば文章も画像も自動で作れし、もう努力しなくても稼げるのではないか」と、そんな淡い期待を抱きながら、私はAIを副業に活用し始めました。
しかし──
現実は想像していたほど簡単ではなく、最初はうまくいかないことばかり。成果も出ず、悩みと試行錯誤の繰り返しでした。
それでも諦めずにAIを使い続け失敗を重ねたことで、徐々にAIとの適切な付き合い方がわかるようになり、現在では副業として安定した収入を得られるまでに成長することができました。
この記事では、私がAIに頼りすぎて失敗してしまった実体験を振り返りながら、そこから得た3つの重要な学びについてお伝えしてうきます。
ぜひ、私の失敗談がAIで稼ぐための参考になりましたら幸いです。
私のAI副業デビューと初期の誤解

インターネット上では「AIを活用してブログ収益化!」「文章作成も自動化で効率アップ!」といった情報が飛び交っており、私も「これで理想的な働き方が実現できるかもしれない」と、大きな期待を抱いていました。
特に衝撃的だったのは、プロ顔負けの文章をAIが数秒で生成してくれること。
試しに「副業 おすすめ」などのテーマで記事を書かせてみたところ、それらしい文章があっという間に仕上がり、私は「これは革命だ」と思い、そのままブログを立ち上げ、記事を次々と投稿していきました。
──ところが、思うような結果は得られませんでした。
アクセス数は一向に伸びず、SNSにシェアしても反応はゼロ。Googleの検索順位にも全く反映されず、「AIを使っているのになぜ?」という疑問と不安が日々募っていきました。
なぜ上手くいかなかったのか?
振り返ってみると、当時の私はAIを「魔法のツール」のように捉えていたのが、そもそもの間違いでした…。
というのも、コンテンツの質や独自性を深く考えず、「AIが書いた文章だから大丈夫だろう」と、過信してしまっていたのです。
その結果、他のサイトと似たような内容ばかりの記事が並び、読み手の心にはまったく響いていなかったのだと思います。
このようにして、私のAI副業のスタートは、期待とは裏腹に「なぜかうまくいかない」と悩む日々の連続でした…。
ただ、この段階での気づきが、のちの改善と成果へと繋がったのだと思います。
私が実際に勘違いしていたことや失敗談、それによって得た学びについてご紹介していきますね。
失敗1:AIに頼りきって、文章が「自分の言葉」ではなかった
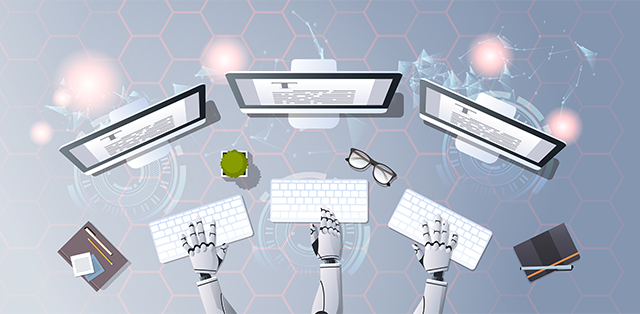
まず、最初に直面した大きな失敗は、「AIにすべてを任せてしまったこと」でした。
当時の私は、AIが生成する文章に対して何の疑問も持たず、そのまま記事として投稿していたのです。「AIが書いたものだから、きっと読まれるはずだ」と信じて疑いませんでした。
自分の声が入ってないことに気づく…
改めて自分の記事を読み返してみると、そこには「私自身の声」がまったく存在していないことに気づきました…。
文章は確かに整っていて、見出しや構成もまとまってはいるのですが、読み手に語りかけるような温度感や、経験に基づくリアリティがまったく感じられなかったのです。
読者は、文章の背景にある「人間らしさ」や「体験の重み」を敏感に感じ取ると言われていますので、私の記事が読まれなかったのは、まさにこの部分が欠けていたからだと痛感しました。
自分の体験や考えを入れて書き直すように改善
AIには文章の「たたき台」を作ってもらったあと、必ず自分の体験や考えを入れて書き直すようにしました。
たとえば、「副業を始めたきっかけ」や「最初に感じた不安」など、「私自身の物語」を加えることで、記事にグッと説得力が生まれました。
AIはあくまで補助的な存在であり、コンテンツの中心には「自分自身の視点」が必要なのだと、身をもって学びました。今思えば、割と初期段階で、このことに気付けたのはラッキーだったのかもしれません。
この気づきは、現在でもブログ執筆やSNS投稿を行う上で、常に意識している大切なポイントのひとつです。
次の失敗談は、「AIの誤情報」によって苦労した事例をお話しさせていただきます。
失敗2:AIの誤情報で信頼を失っていた

次に私が経験した大きな失敗は、「AIが出力した情報を鵜呑みにしてしまったこと」によるものでした。
ある日、ブログ記事の中で副業関連の制度やサービスについて解説する内容を書いていたのですが、その際にAIから得た情報が、実際には古く誤ったものであったのです。
まさかAIが間違うわけがないだろう…
そう過信したまま、事実確認もせずに記事を公開してしまったのです…。
読者の方から「この情報は古くて正しくない」という指摘を受け調べ直したところ、その通りでした。
この失敗がなければ今の私はいなかったので、本当にありがたい指摘でした。あのまま事実確認をせずに投稿を続けていたらと思うとゾッとします。
記事を公開前に情報を確認することが大事!
それ以降は、AIが出力した情報に対して必ず公式サイトや専門家の見解などを確認するようにするようにしました。
また、記事の中「202X年〇月時点の情報です」などと明記し、正確性と透明性を意識した文章づくりを心がけるようにしていきました。
AIは非常に便利なツールですが、万能ではありません。
特に最新情報や法律・制度に関する内容は、人間の目で確認し、責任を持って判断する必要があるのだと強く学ぶことが出来た経験です。
次は、AIに任せすぎたことによって「創造性」を見失いかけた失敗についてお話しさせていただきます。
失敗3:AIに任せすぎて創造性が失われていた

3つ目の失敗は、AIに頼りすぎた結果、自分自身の「創造性」を見失いかけたことです。
副業において効率化するのは非常に重要です。しかし、効率を求めすぎたあまり、すべてをAIに委ねるようになってしまいました。
記事の構成やキャッチコピー、さらにはSNSの投稿文まで、AIに頼れば一瞬で形にはなりますので、その便利さに慣れてすぎて、「自分で考えること」そのものを放棄していたのです。
もはや自分で考えるのを放棄してしまっていた…
たとえば、あるときに作ったブログ記事では、構成も文章もすべてAIが提案したものをそのまま使い、私は最終チェックすら疎かになっていたんですね…。
改めて記事を読み返してみると、内容がなんだか他人事のようになってしまっていたのが、読者からの反応がなかった原因だということに気付きました。
読者に響くコンテンツというのは、「自分の頭で考え、感じたこと」からしか生まれません。
AIはあくまでアイデアの補助や、視点を増やすツールに過ぎず、創造の核は人間自身の中にあるべきだと痛感した失敗でした。
AIを使う前に自分で考えてみるように改善
記事やアイデアを考える段階で「必ず自分でも考える」ということを意識するようにしました。
AIには自分のアイデアを整理したり、視点を補完したりする役割を担ってもらい、「考える→作る→AIで補う→見直す」といった流れを意識するようにしました。
もちろん、アイデアに詰まったらブログテーマをAIに考えてもらうということもしていますが、AIにたくさんアイデアを出してもうためにも、まずはざっくりでも良いから必ず自分が何をしたいのか考えることを意識するようにしました。
こうすることでAIに記事作成をお願いする時でも自分の言葉を入れやすくなります。
この流れを組んだことで、創造性と効率性のバランスを取り戻すことができました。
この経験から、「AIに仕事をさせる前に、自分がどうしたいのかを明確にすること」の大切さを学びました。
それは今も、すべての作業において基本として大切にしている姿勢です。
失敗から見えた、AIとの前向きな付き合い方

これまでお話ししてきたように、私のAI副業は決して順風満帆ではなく、多くの失敗と学びの連続でした。
ですが、その経験があったからこそ、AIを効果的に活用し副業で成果を出すための大切な土台となったのも事実です。
まず何よりも意識するのは、AIを「万能の魔法の道具」としてではなく、「あくまで補助的なツール」として位置づけることです。
AIは膨大な情報処理能力とスピードを持っていますが、最終的な判断やオリジナリティを生み出すのは、常に人間である私たちの役割です。
また、失敗を通じて学んだのは、「情報の正確性を自分で必ず確認すること」の重要性です。
AIが提供する内容を鵜呑みにするのではなく、公式情報や信頼できる一次情報を必ず調べることで、読者からの信頼を築けると実感しております。
さらに、自分の経験や思いを必ずコンテンツに盛り込むことで、AIには真似できない「人間らしさ」と「創造性」が加わり、読者の共感を得やすくなることも忘れてはなりません。
これらの学びを踏まえ、現在の私のAI活用法は「自分の頭で考え、AIを上手に使って効率化し、最後は人の手で磨き上げる」というバランスを大切にしています。
発明王として有名なエジソンが残した「私は失敗したことがない。ただ、1万通りの、うまく行かない方法を見つけただけだ」という言葉があります。
ただの失敗と捉えるのではなく、経験のひとつとして前向きに捉えれば、必ず次の成功につながります。
最後にまとめると、
- 自分の言葉を入れること
- 情報の正確性を自分で必ず確認すること
- 自分の頭で考えること
失敗から学んだ私の経験が、正しい使い方を身につけ、自分らしい副業スタイルを築いていくための一助となれば幸いです。
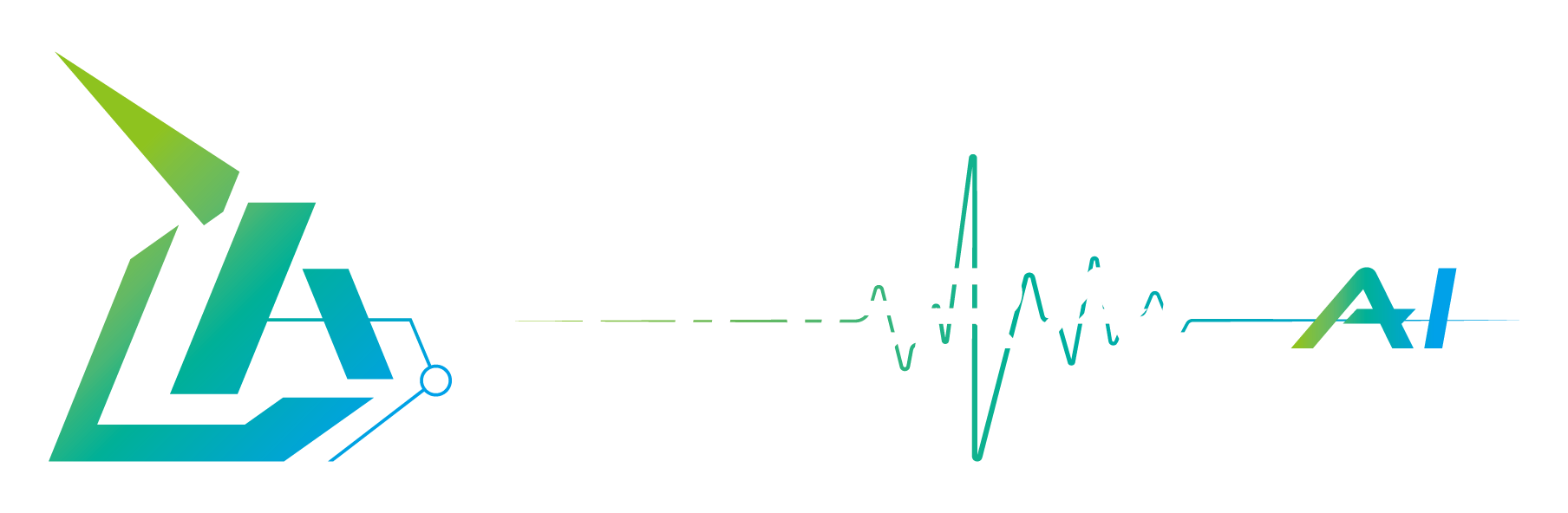

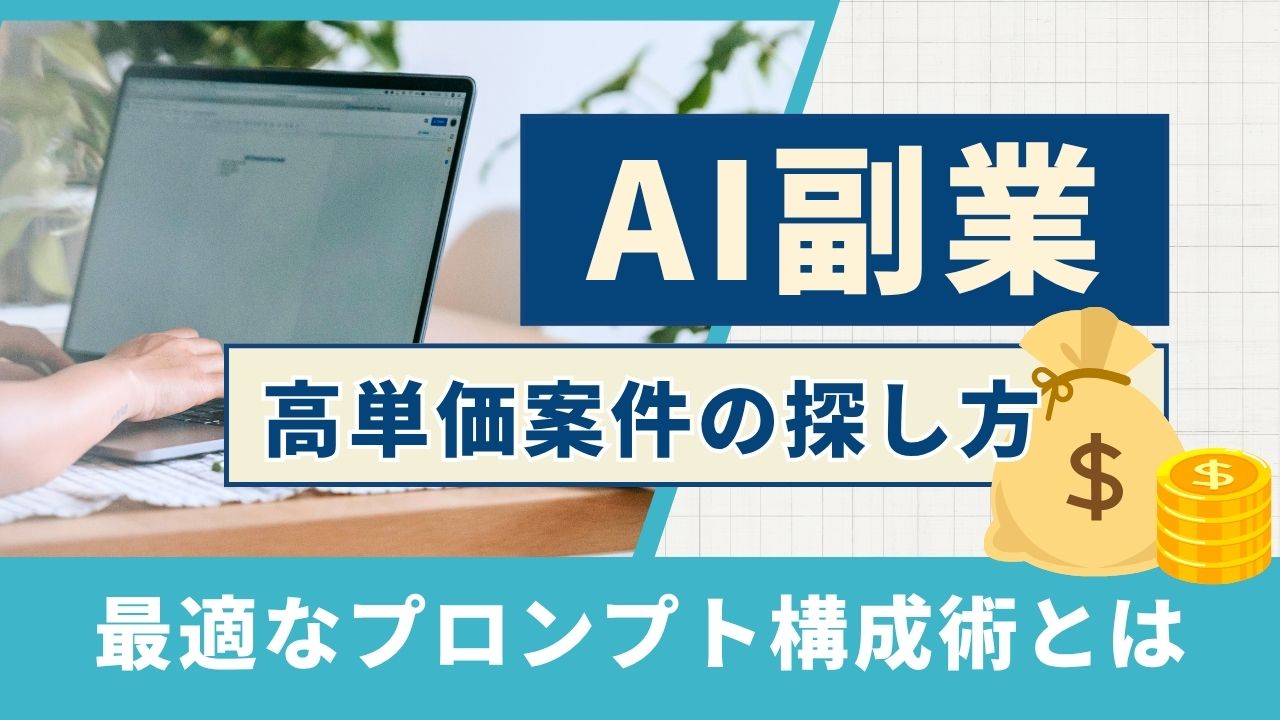
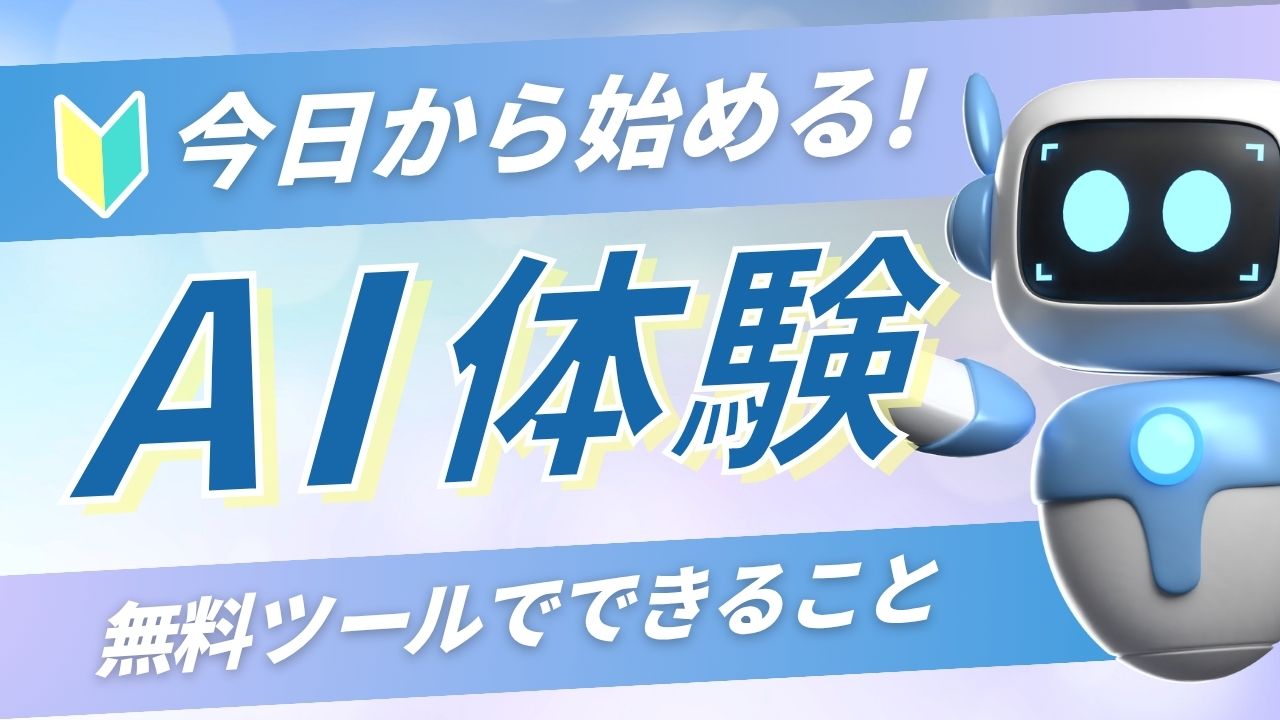
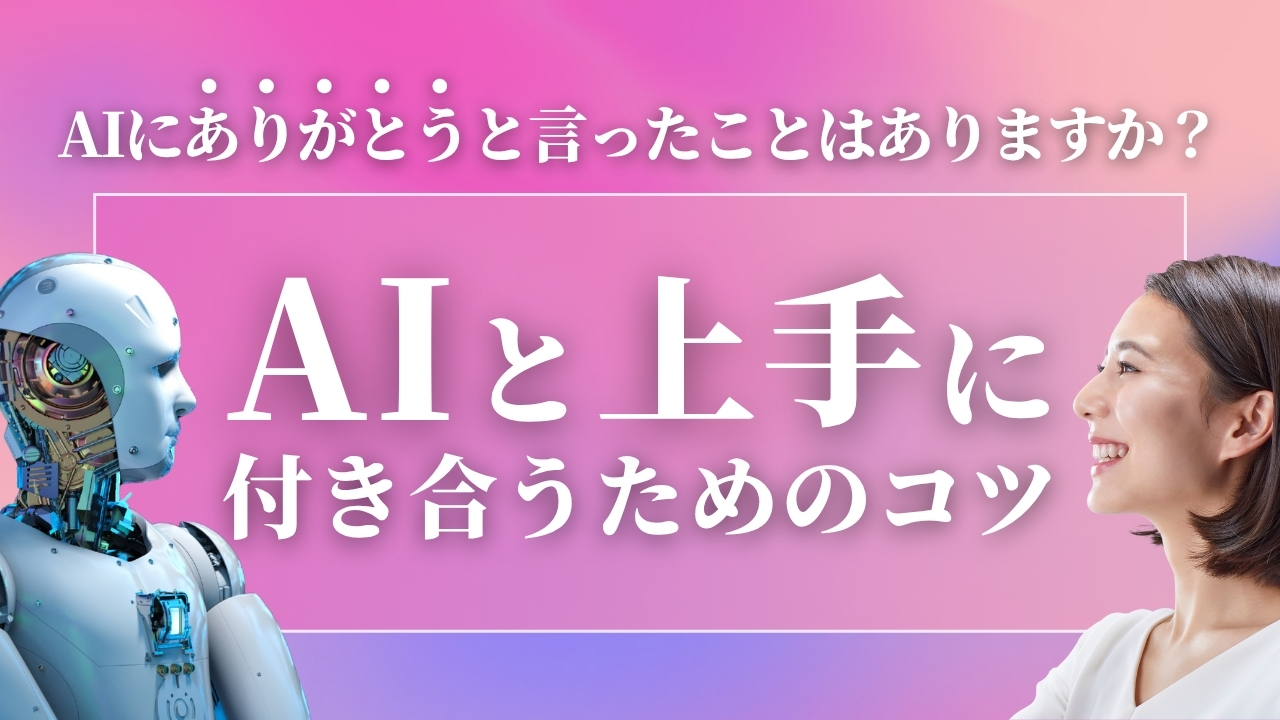

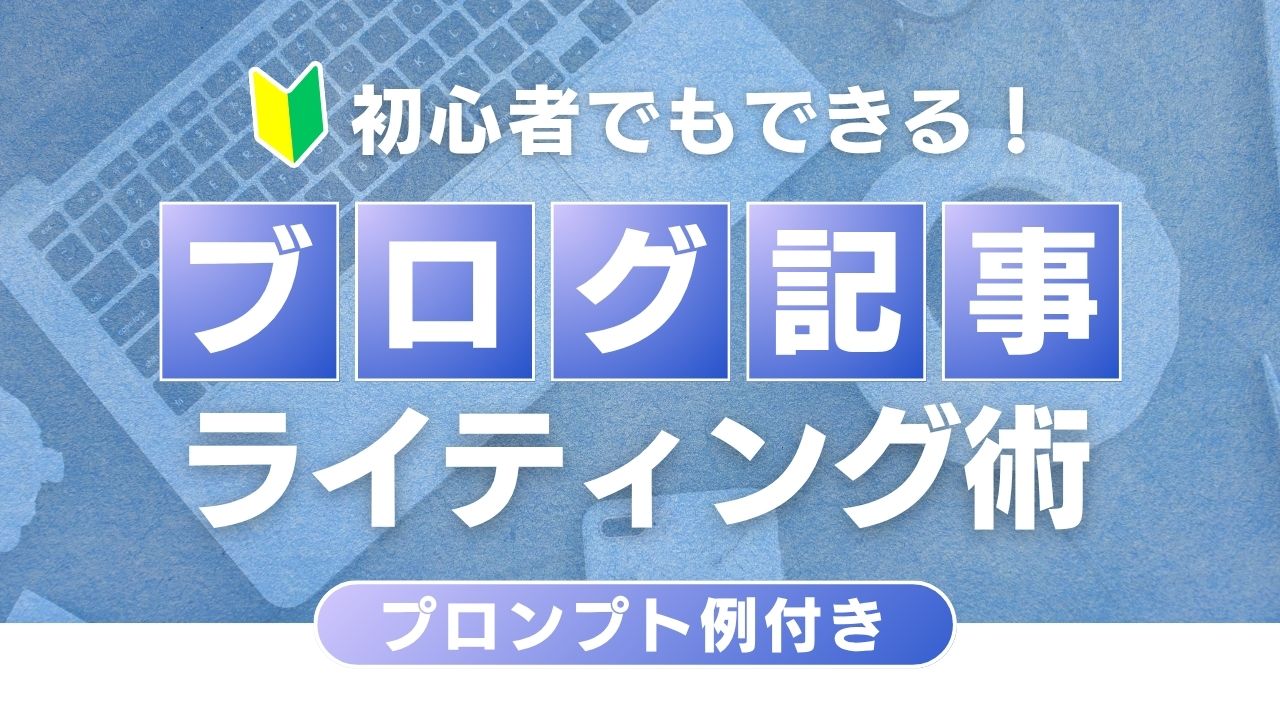
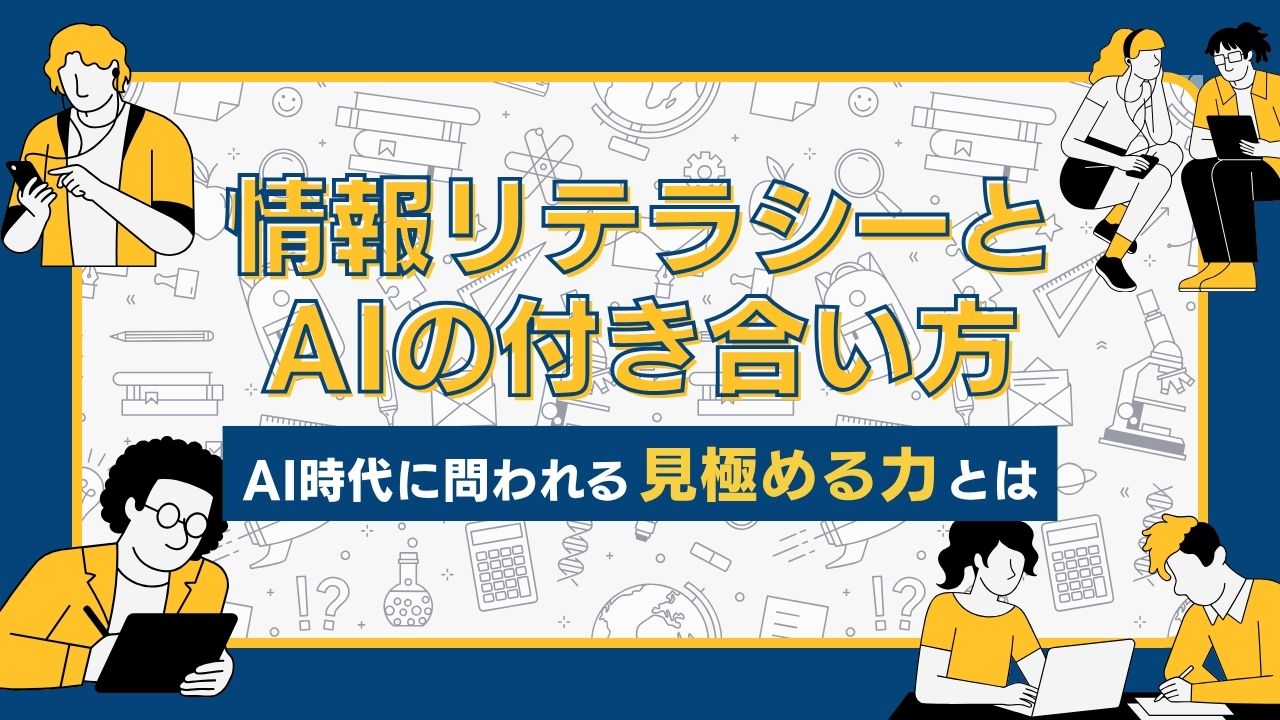
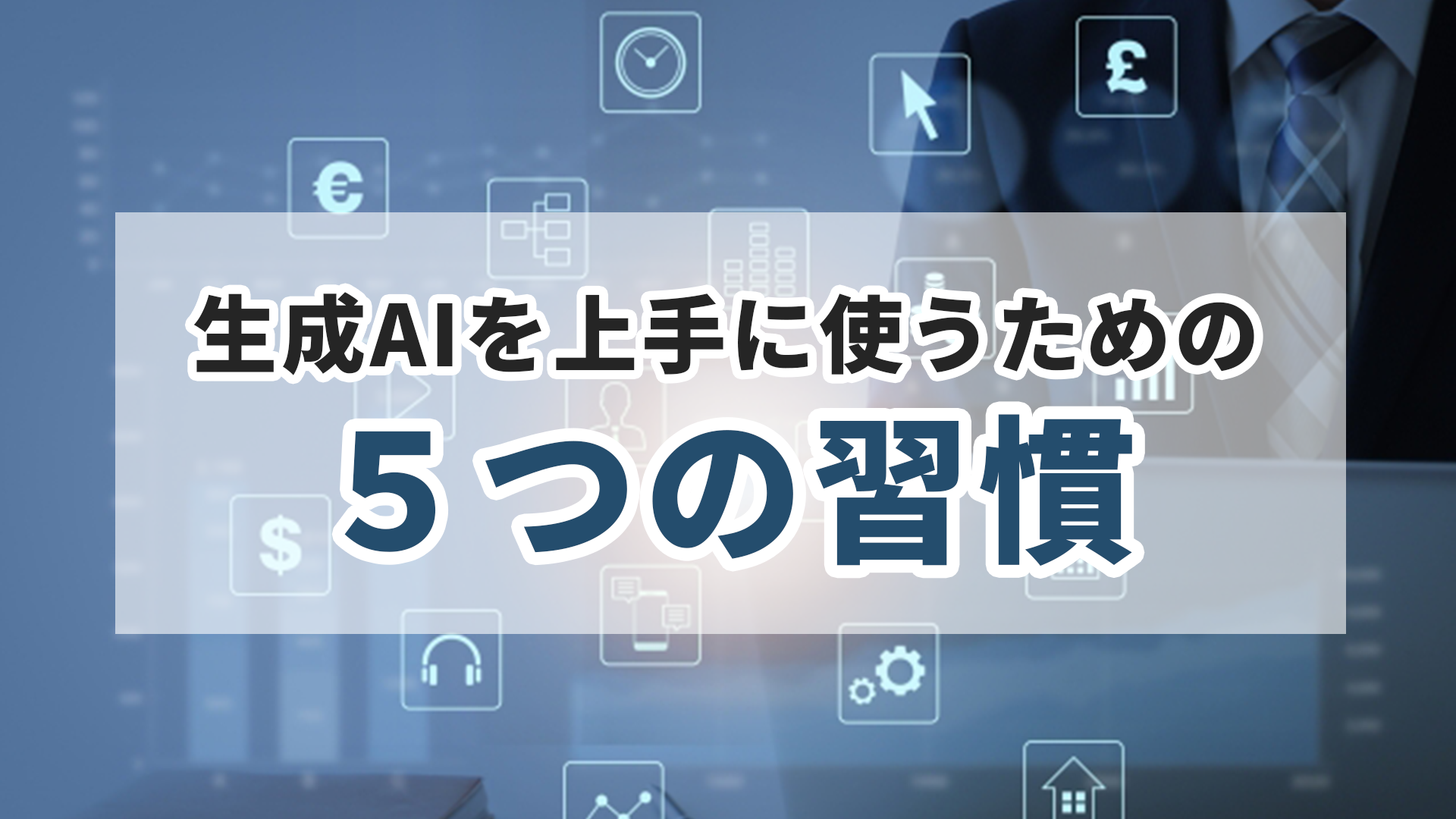

コメント